「ゼロの告白」第二章/第一話 [押入倉庫A]
小春日和のある日、男は小さな包みを持たされて桜椿に囲まれた小高い丘にある『椿山荘』に足を運んだ。そこに集まっていたのは上品な出で立ちをした紳士淑女の面々だったが、その装いとは裏腹に何か妖しげな品の悪さを漂わせていた。男はその中の一人の長老ともいえる人物に包みを手渡して会釈をした。中身を既に知っているのか、長老は何でもない様な素振りで受け取ると奥の部屋に引っ込んで行った。
後に政財界を巻き込む疑獄事件の種となった株券の束だったとは、受け渡しを任されたその男は知る由もなかった。

まだ四十前の男には自分の配達した小包が日本を揺るがす事件の種になっていようとは考えもしなかった。そもそもそんな事件が自分の日常の周辺で起こることさえ考える事もなかった。しかしその後、身近だった『佐山急配』東京本社にキナ臭い噂が立って渡瀬社長が検察に取り調べられたという噂が聞こえてくると、関係していた男も胸の内が穏やかではなかった。そしてまるでドラマの様な現実が目の前で起こっているのを知った時、不思議な幻惑と覚醒の戦慄を感じたものだった。名の知れた政治家や経済人が逮捕されて消えてゆくのを見届けて男は故郷(いなか)に帰って事件を記憶の中に封印したのだった。
「ゼロの告白」第一章/第十話 [押入倉庫A]
原風景を辿ってみれば、両親が行商の共稼ぎ夫婦だったために、幼い頃から他人の家に転々と預けられた家が天理教の会所だったこともあった。お堂の階段を上がった所に丸い囲み火鉢のようなものがあって、そこで年老いたお婆さんに世話してもらっていて微細な事は覚えていないが何となく非日常的な空間の印象だった。その体験からか宗教臭いと言われるものに少しも抵抗感が無く忌避意識も湧くことがなかった。
会所の様な所に聖書勉強会という名目で週に一回通っていたのだが、教義の説明が理論的であり科学的だったところに共感を覚えて、今の自分にはそれが話を聞くに足るものだったようだ。人間の脳は殆ど無限に近いくらいの能力があるのに使われていないという話や、古代の人間はもっと永く生き長らえるだけの寿命があった話などを織り交ぜて“永遠の命”につての語りがあった。以前なら醒めた気分で聞いていたであろう説話が、どういった訳か素直に聞き入れられてそんな自分に驚かされてもいた。

改めて振り返ってみると数々の間違いと、許される事のない罪を犯してきた様な気がしている。それは全く個人的な事で中には既に鬼籍に入った者もいて誰に懺悔する事も出来ないものだ。人生で背負って生きてゆくものの中にはそんな不条理にも似た苦痛の念もあるが、それらもまた絶対的ではなく“罪の足音”の様な飽くまでも自分自身の創造した観念なのだろう。
この世に生を受けてから延々と時間は流れ、蓄積された思索は行き着くところ限りなくゼロに近づきそして終焉の門を叩こうとしている。目の前にはもう少しも若くない自分が立っている。様々な寄り道をしてきたが、そろそろ自分自身の答えを用意しなければならないようだ。
「ゼロの告白」第一章/第九話 [押入倉庫A]

社会に守られていない女の抵抗ほど男にとって微力なものは無かった。女もその無力さを知っていたから申し訳程度の抵抗をするだけで、結果が目に見えていたかの様に体を任せた。決して心では受け入れていないのに体はまるで抵抗をしない様相は、日常の表層と深層を垣間見た様でセックスを終えた男を空しい気持ちにさせた。
ただ若さの捌け口を処理しただけの感覚の男にとって、帰宅した若者が憤慨して絶交を言い渡した事が予想外だった。共有意識の理解を認め合っているという誤解から成り立っていた幻想を砕いて、若者と自分を取り巻く全ての環境から繋がりを断絶されたような気分になった。
相手の存在も自分と云うフィルターを通してでしか認知する事は出来ないのだ。自分のイメージした偶像に当てはめて理解したような気になっている、それが人間の“愛と理解の限界”なのだと思った。手ごたえのある何かを求めて生きていた筈が気がつけば周を取り囲む幻想の中に浸っていた。遠くに見える微かな夢想もきっと蜃気楼の様なものに違いない。近づけば少しずつそれが幻想である事に気づいてゆくのだろう。
「ゼロの告白」第一章/第八話 [押入倉庫A]
練習が終わると女は若者のそばに寄り添った。軽い談笑をすると二人は男の方に歩み寄って言った。
「これから一杯飲みに行くけど、付き合いませんか?」
若者とは毎度会釈を交わす程度で女とは初対面だったが、戻っても何をする当てもない男はこのまま夜の街を彷徨うことにした。男二人の間に幼な顔の女が一人、妙な取り合わせが連れ添って飲み屋を数軒はしごして帰路に着いたのは明け方の五時過ぎだった。
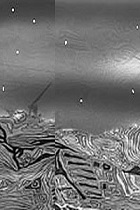
男は身を起こすと狭い部屋から外に出て辺りを見回してみた。所どころに民家が点在してはいるが周りは草萌える原っぱに囲まれ閑散として静かなものだ。「こんな環境の中で若者は自活しながらドラムプレーヤーになるため日々奮闘している」そう思うと羨ましさと同時に自分に対しての焦りの様な気分に襲われた。今すぐにでも何かに向かって突っ走りたい気持ちだったが、絵を描くといっても何のテーマも見つかっていない自分がそこに在るだけだった。
「少しここに留まってみよう…」そんな考えが頭を巡らしながら軽く深呼吸をして部屋に戻ってみると二人が目覚めてタバコをふかしていた。若者は夕方からのバイト出勤で、女の方はそれまで一緒に付き合う様子なので三人で取りあえず都心に出て食事を取る事にした。
昼下がりの中央線の車内は通勤時間帯とは比べものにならないくらい閑散としている。三人は寝起き状態のままの崩れた格好でシートに座ってとり止めのない話をしていたが、男が唐突に話を切り出した。
「ここで絵を描きながら暮らしたいのだけど、一緒に…どうだろう?」
「いいんじゃない、私も半同棲みたいなもんだし…」女がそう言うと若者も当たり前のように受け入れた。
「ゼロの告白」第一章/第七話 [押入倉庫A]
しかし人というのは不思議なもので、枠からはみ出せばはみ出したで、自分を律する何か思想や主義といったものを求める様になってくる。固定観念も持たず何に立脚する事もなく生き続けるという事が人間には出来ないものなのだろうか。自分の中心にゼロの存在を受け入れる発想は人間にとって難しいことなのだろうか。

その日もバイトの皿洗いの仕事が終わってアパートに帰る途中、いつもと変りないコースで夜更けの公園を通り抜けようとした時だった。公園の片隅で何やら戸板を叩くような音が響いている。パシパシという乾いた音に引き込まれて覗いてみると、一人の若者がドラム練習用のボードを叩いていた。何か妙な共感を覚えた男は、練習風景を眺めながら若者の前に腰を下ろした。無心にドラムボードを叩くその若者は男よりも四、五歳ほど年が若そうに見えてたがボードの乾いた音だけが響く二人の間には無言の時間が流れてゆくばかりだった。
十五分ほど経った頃だっただろうか、汗を拭いながらふうっと呼吸を整えてスティックを置いた若者と男は初めて目を合わせた。軽く会釈をした男は立ち上がって近づきながら声を掛けた。
「ドラムの練習ですか…こんな夜更けに」
見ればわかるような間の抜けた問い掛けだったが気心も知れぬ相手を探るひと言とはそんなものだ。
「アパート部屋ではドラムの練習が出来ないもんでね」
無口で近寄りがたい見かけと違って意外と人懐っこい表情の返事が返って来た。居酒屋でアルバイトをしながら昼間はドラムのレッスンを受けているらしい。師匠は新宿『ピットイン』でも演奏している有名なジャズ・ドラマーだというから、プロを意識した本格的な指導を受けているのだろう。将来に向かっての確固とした道を掴んでいるその若者が羨ましかった。
しばらく話をしている間に二人の間には親近感が湧いてきた。互いに故郷を離れて頼るもののない都にやって来た事や、世間の常識からかけ離れた生き方をしている部分で共感し合ったのかも知れない。はぐれ者同士の妙な信頼感さえ生まれたようだった。若者の叩くドラムボードの歯切れよさにも魅了されて仕事帰りに公園に立ち寄る事が多くなった。
「ゼロの告白」第一章/第六話 [押入倉庫A]
「卵が先か、鶏が先か」という言い回しがあるけれど、どちらが原因とも判断つかない因果関係はよく見られる事で、この男の場合も死の淵に立たされる経験は何処から来るものなのかは実は良く分からないでいた。生涯に何度も体験して来た生死の境い目はもしかすると幼い頃の流転の生活がそうさせたのかも知れない、いやそうに違いないとも思えるのだった。
スリルの快感を味わっていた訳ではない。その行為は言い知れぬ不安と恐怖に襲われる逃れたいほどの苦痛だったが、それなら何故敢えて求めるのかという問いがこの男の個性の不条理な部分でもあった。学生の頃は様々な自己矛盾に悶々としながらも前に進まなければ落ちこぼれてゆく時代の強迫観念に追い立てられ、その理由を探るよりもとにかく前に進む行動あるのみという結論で行くしかない時代でもあった。

年少の頃は高いビルから身を乗り出したり、瓦屋根から飛び降りてみたりといった幼稚な驚かしで済んでいたが、社会人になると車での危険な賭けレースをしたり、街のヤクザに絡んでみたりという荒業に発展していった。時には正義感を看板にすることもあったが、本当のところは“自分の存在の危うさ”への挑戦だった。ひとつ間違えれば力でねじ伏せられる社会への恐怖心がこの男をそこまで駆り立てる理由でもあった。

「ゼロの告白」第一章/第五話 [押入倉庫A]

この頃の男は何に対しても貪欲に吸収する欲求があるだけで、だからこそ何に対しても不満を感じることが無かったようだ。どんな処遇を受けてもどんな環境に置かれても、まるでそれを楽しんでいるかのようにさえ見えるある種の不敵さを持っていた。幼児期から大人たちの間を転々と順応を強いられて過ごしてきた少年時代は、彼にいつ如何なる時も場に溶け込んでその中核を掴む才能を磨いてくれたようだった。
まるで流れ者の様な気分で毎日を生きていた事もあった。青春を過ごした’60年代から’70年代にかけては時代そのものが流動的な感覚の時代だった事もある。生まれて来るものの全てが新鮮な価値として受け入れられた時代。何もかもがどんどん蓄積して後の飽食の時代に突き進む時代とも言えた。
「ローリング・ストーン」という言葉が、イギリスのロックバンド名のみならず、いたるところで叫ばれていた時代でもあった。新しい時代に向かって混迷の続く状況に、未来の成り上がりをめざして若者たちがハングリーである事を誇らしげに掲げた時代…。都会に佇むこの男もゼロからの脱却を心に決めていた時期でもあった。

「ゼロの告白」第一章/第四話 [押入倉庫A]
行商で朝早くから家を空ける両親に物心ついた頃から他所に預けられて一日を過ごす暮らしを習慣づけられてきた。幼稚園に入園するまでに数か所の家庭を転々としたがその中には酷い家族もあり、いじめや差別の他にも満足に食事も与えられずに栄養失調に陥るという事もあって決して楽しい日々という訳ではなかった。

幼い頃の育つ環境や生きてゆく条件というものは一方的に与えられるもので 決して選べるものではないのだが、その後の成長段階で自分の与えられた条件をどのように解釈して捉えてゆくかは個人の資質によって異なっているものだ。この男は神経質で臆病な性格だったくせに、どういう訳かおっとりとした雰囲気を漂わせて周りの環境に溶け込んでいるかのように見えた。彼は無意識のうちに身の回りの状況から自己を肯定させる要素を見い出す“目利き”を発揮してきた。それは環境に順応しながら生き抜いてゆく生きものとしての生存本能なのかも知れない。男は「肯定的に受け入れる」という考え方こそが生存の秘訣としてふさわしいと選択してきたのだった。
故郷を離れて東京に出て来た事もこの男には“どんな境遇に際しても生き延びてゆく”という事へのひとつの挑戦だった。それは幼い頃から自覚して来た「預りの身」を現実に即させる経験だったのかも知れない。幼少の頃から人質として他国の城を転々とした事が、我慢強く時期を待って後に天下取りの夢を果たした徳川家康の性格形成に影響を与えている様に、相手の懐に入って機を待つ生き方は幼い頃からの経験で育つものの様だ。

生きてゆくためには食べるものと寝るところの確保に、新聞の求人欄で目についた住み込みの仕事に応募することにした。電話の指示に従って辿り着いてみると、そこは場末の俗称“トルコ風呂”と呼ばれている風俗店で、目隠しされた門を入ってすぐの階段を上がってゆくと二階のロビーらしき所にはすでに二人の求職者が集まっていた。
どうやらこの店の他にもチェーン店があるらしく、ボックス車に乗り込むと都内と郊外数か所の店を廻ってそれぞれの求人応募者を拾いながら就業場所まで運ばれて行った。延々二時間近くも経っただろうか総計八人の男たちを乗せた車は県境を越えて夕暮れ薄暗くなった千葉・松戸の郊外に到着した。
殺風景な一角に無機質なガレージ風の建物が目に入った。すぐ隣には二階建てのアパートが建っていてこれが寝泊まりするための宿舎らしい。ガレージのように見えた建物の中には大きなドラム状の洗濯機と乾燥機がそれぞれ二台ずつ置かれていた。どうやら仕事というのは風俗店で使用済みのタオルを回収してここで洗い物するという事がようやく分かってきた。住み込み食事付きであり就いた仕事は男たちの精液にまみれたタオルを洗濯するというものだったが、とにかくこれで食う所と寝る所は確保してゼロからの生活の第一歩を踏み出すことになった。
「ゼロの告白」第一章/第三話 [押入倉庫A]
【宿無し】
昭和五十二年十二月。寝袋と現金5万円だけ持って夜行バスに飛び乗り、東京駅丸の内に着いたのは翌日の早朝だった。
駅出口の階段を下りて地下の『東京温泉』でひと風呂浴びるとそれまでの緊張感が和らぎまるで気ままな旅に出たような錯覚に襲われた。根っから呑気者の自分自身に少しばかり呆れた気もしたが、すぐに気を取り直して冬の寒空に顔を向けた。
都会の電車は既に早くから人々を運んでいる。ふらりと飛び乗った環状線は気がつけば渋谷ハチ公像の前に来ていた。
通勤時間にはまだ早い当時の早朝ハチ公像前にはその日の仕事を求める人たちが集まる場所でもあった。俗称『ニコヨン』と呼ばれる日雇い労働者を何処からともなくやって来たトラックが乗せてはそのまま工事現場に直行するという、労働基準法を完全に無視した無法の労働市場がそこにはあった。

もう少し時間が経てば大都会の通勤ラッシュにこの界隈も雑踏の嵐と化す。男はハチ公像前に腰を下ろしてこれからの行く先をぼんやりと想ってみた。何か計画を持って出て来たわけではない。まさに行き当たりべったり風が吹くままの股旅だ。
初めての街に足を踏み入れたら、まずは駅の構内で体を休ませながら街の空気に馴染ませるのがパセンジャーとしての異邦人のセオリーである。
知り合いもなく顔見知りもいない誰から相手にされることもない空気の様な存在の自分が、何かの種を蒔いて育ててゆくにはまず地慣らしから始める事が妥当な方法だろう。子どもの頃から様々な場所で転々と預けられてきた習性から少しずつ環境に馴染む生き方を最良の術として身につけてきたようだった。
幼児期は何に対しても臆病で内向きがちだったこの男が、小学校上級になる頃には多くの級友から慕われて学年のリーダー格になっていようとは周りの誰もが思いもしない事だったが、その変化には原因があった。
漫画の中に登場するヒーローたちに目覚めた事が始まりだった。子供心にも憧れと願望というものがある。日々の現実が息苦しければ益々その思いは強まるだろう。男は幼少の時代にその窮屈さから脱却する空想世界のヒーローの生き方に自分を重ね合わせる道を見つけたのだった。

そんな訳もあって少年は毎日のように近くの貸本屋に通った。まだ幼かった彼には刺激的とも思える青年漫画の数々が並んでいたが、早熟だった彼は貪るように漫画を読んだ。
大人たちは子どもが漫画を読むことを娯楽の一種のように解釈していたがこの少年に限ってそれは違っていた。成人してからも少年には娯楽として物事を捉える感覚が芽生えなかった様に、すでにこの時期から全ての楽しみは何らかの実利を見つけてこそ意味のあるものだった。
“たかが漫画、されど漫画”少年の時代には教育的観点から悪書として位置付けられるような社会的地位の漫画ではあったが、彼は自己を投影するメディアとしての潜在的な可能性を発見していた。現実的日々での満たされない欲求不満や裏切られる思いを漫画の世界に於いて解消する術を身に付け始めていた。
初めての都会生活とも言えるものが、宿無しの浮浪者然とした生活スタイルである事は改めてこの男の宿命的な将来を暗示させるものだった。
職も無く所持金も乏しい当分の生活はとにかく出費を抑えた暮らしをするしかない。昼間は新聞の求人欄や「アルバイトニュース」などで仕事を探し、夜になれば代々木公園で野宿をする生活が日課となっていたが、若さのせいか少しの不安も感じていなかった。それどころか「どんな環境でも生き抜ける人生」の実践の入り口に今まさに立った気分で高揚している。
この頃の男にとって『ゼロ』であることは未来への期待と同時に、恐れを知らぬ一種の誇りでもあった。
「ゼロの告白」第一章/第二話 [押入倉庫A]
【若気の日々】
振り返って考えてみれば、目に見えて蓄えられたものが何も無い男になっていた。
次から次へと流れるように生きてきた。その時その時を真剣には生きて来たが、何も残してこなかった。
“次につなげてゆく、蓄積してゆく”という計画的な生き方をして来なかった自分に気がついた。
「人生は一度きり、チベットの砂絵のようなもの」とうそぶいていた男だったが、時には通俗的な気分で見得を切りたくなる事も事実で、何も形のあるものでは証明の出来ない事を知ったときに軽い疑問が頭を過ぎる事がある。
「私が確信しようとしているものは一体何なんだろう?」
その男は自分の人生を自分の手でしっかり掴んでいるという自覚がある。子供の頃に恐れていた事々がひとつずつ解消され、堂々と生きる感覚に支えられている。もしもここで人生が終わるのであれば、それはそれで良いとも思える心境である。しかし、まだまだこれから物語りが続くとなると、今後の展開と身の振り方を考えて行かなければならない。目に見える実績らしきものも、社会的地位らしきものも何も持ち合わせていない自分自身に対して、本当に私は泰然自若としていられるのだろうか?
そしてこれから先も、このままで何も築き上げる事無く、自分なりの答えを抱きながら淡々と生き続けてゆけるというのだろうか?

もがきながらも辿り着いた終の棲家は悩みも消え失せた楽園のように思えたが、暫らくするとそこにも居続けられない自分の業の様なものが目醒めてくるのだった。
「何も求めない」という気持ちだけでは生きられないものなのか?放浪の果てには待つものも無く、郷から遠く離れ続ける定めでしかないのだろうか?
様々なものを克服してきたつもりだった。
時には敢えて自身に傷をつけて免疫力を高めるような行動も取った。傍から見れば自虐的なマゾヒストに見えたかも知れないが、本人には全くそんな趣味は無かった。
敢えて逆境に飛び込むことが自己を磨く道であると思っていたに違いない。『艱難汝を玉にする』という何処かで聞いた言葉を金科玉条のように抱き続けていた。
しかしそれらは全て若気の至りであったと、今になって痛感するようになった。
自分自身を傷つけて良い結果を生むという様なことは無い。
敢えて主流の正道を選ばず、社会の底辺とか蔑まされている世界とかに好奇心で体を預けるような生き方は、実はコンプレックスの裏返しでもあったと後々発見する事になる。

だが時代はまだ昭和の五十年代で、恐れを知らぬ無知無謀な若輩者は単身寝袋を肩に下げて花の都・東京に向かったのだった。
それは男にとっては武者修行の様なものだったが、実際には一般社会の枠組みから離脱させてその後の人生を決定づける岐路でもあった。
「ゼロの告白」第一章/第一話 [押入倉庫A]
【男の独白】
その男は若い頃から「どんな環境でも生きてゆける自分になりたい」と思っていた。
だから、時として自分らしくない自分を装って、自分にふさわしくない場所に飛び込んだりもした。
常に様々な問題と直面したけれど、守りの姿勢を持たない私は緊張感こそあれ、それ程の恐怖心も感じていなかったように思う。
青年時代に海外で放浪の旅をしたせいか、見知らぬ新しい土地に飛び込むことには慣れっこになっていた。見知らぬ土地に、馴染みのない人たち…そんな出会いと別れの連続の日々を過ごしていたのは、青春の多感な時期だった。
その何にもしがみ付かず、何も残さない生き方は男にとっては“自分の本質と最もかけ離れた生き方”であった。

朝早くから晩まで両親が行商に出て不在の毎日であったために、3歳の頃から他所の家庭に半日預けられて暮らす日常であった。
預けられた家庭も一箇所ではなく、幼稚園に通うまでの3年間に4つの家庭環境を転々とした。ある家庭でそこの子供にいじめられた事もあれば、粗食をあてがわれ続けて栄養失調になり掛けた事もあった。常に新しい環境と新しい人間関係の中で“やり直しの繰り返し”を続けてきたのだった。
そんな彼にとって、一日の終わりに迎えの母親と一緒に帰る我が家は天国であった。貧相な借家の建物で、粗末な蛍光灯一本以外に室内には裸電球がぶら下がっているだけだった。入り口のガラス戸を開けると小さな土間の片隅が狭い炊事場になっていて、水道も引かれずガス焜炉が一台ポツンと置かれているだけだったが、天井からぶら下がるソケットに繋がった電球が、大人になった今でも暖かな団欒の風景として焼きついていた。

我が家では王様だった男は、この安息をいつまでも所有したいと願うのが当然の事のように思えたが、何故か生活の一切を捨てて家から離れる事を願望として抱いていたらしい。
人一倍所有欲の強い男だったが、一人息子として大事に育てられた彼にとっては、所有は約束されたものであり誰からも脅かされるものではないと安心し切っていた様子で、心の奥底には執着心と所有欲を抱きながらも表面的には抜けたような大らかな雰囲気を漂わせていて、ガツガツとした物欲しそうなところは感じられない子供だった。






